さて、今回のお話は!
「自分がいなくなった後のために遺言書を書いておきたい」、「家族が遺言を書こうとしている」、このページをご覧になっているのは、このような方ではないでしょうか。
今回は、「遺言書を書きたいけど何からすればいいのかわからない」といった方のために遺言書についてわかりやすく解説したいと思います。
遺言書の種類を知ろう!
遺言書には主に3つの種類があります。それが、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の三種類です。まずは自分の目的に合った遺言書の種類を決めましょう。ただ、「秘密証書遺言」についてはデメリットが目立ち、用いられることが少ないため、省きます。
自筆証書遺言は読んで字のごとく自分で書いて残す遺言書です。紙とペンと印鑑さえあれば完成します。ですので、「費用をかけずに手軽に作成したい」という方に向いています。
ただし、お手軽な分以下のようなデメリットがあります。
- 相続手続きの際に家庭裁判所の検認手続きが必要
- 偽造・紛失・盗難・未発見のおそれがある
- 間違いや不備があった場合、無効になる可能性がある
- 死後、相続人同士で争いになる可能性がある
上記のようなリスクが伴いますが、現在は法務局の自筆証書遺言保管制度を利用することで上記1、2のデメリットはクリアしたと言えるため、自筆証書遺言も利用しやすくなってきたと思います。
ただ、遺言保管制度は遺言書の内容や遺言者の意思能力まで保証してくれませんので、「遺言書の内容に不備がある」、「強引に遺言書を書かせたのではないか」、「遺言書の作成年月日にはすでに認知症で意思能力が無かったのではないか」などの理由で、無効やトラブルになる可能性は十分にあります。
次に公正証書遺言ですが、一言でいうと方式の不備がなく、紛失や改ざん等の心配がなく、検認手続きも不要で、相続人同士の争いが極めて起こりにくい遺言書です。公正証書遺言は、証人二人以上立会の元、公証人(裁判官、検察官、弁護士を長く務めた法律の専門職)が作成し、遺言書の原本を公証役場が保管するシステムなので非常に信頼性が高い遺言書になります。
ただ、デメリットとしては
- 公証人との打ち合わせや公証役場への出頭など手間がかかる
- 申請に必要な書類を準備する必要がある
- 証人を二人用意する必要がある(推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族は不可)
- 作成に手数料がかかる(料金は遺言の目的とする財産の価額によって変わる)
それぞれ一長一短ですが、簡単にまとめますとコストをとるか確実性をとるかになります。自分がいなくなった後、大切な人たちがどのような関係を築いていくかを想定して決断するとよいでしょう。
自筆証書遺言の書き方
では、自筆で遺言書を作成する際の要点を見ていきたいと思います。
①全文自書する
パソコンなどで作成した遺言は無効です。印字された文字は遺言者の意思が読み取りづらく、偽造なども容易であるためです。他人による代筆や自筆した遺言書を映した写真やコピーなども認められません。
②相続財産や人物の書き方
民法では財産や人物の記載方法として、特段の決まりがありません。記載が曖昧で遺言者の意思を客観的に確定できない場合は効力を生じません。また、後の紛争防止のためにも、人物や財産は具体的に特定しておくべきです。例えば、土地の場合はその所在、地番、地目、地積、銀行預金の場合は銀行名だけでなく、支店名、口座の種類、口座番号、口座名義人といった事項を記載して特定する必要があります。
例. 遺言者は妻〇〇に次の財産を相続させる。
遺言者名義の土地
所在 静岡県伊東市一碧湖畔二丁目
地番 25番
地目 宅地
地積 100.25平方メートル
ただ、2019年1月13日に施工された改正相続法により、相続財産目録をパソコンによる入力の他、登記事項証明書や通帳の写しを添付しても有効と扱われることになりました。その場合はそのページには署名・押印が必要です。財産の量などを考慮して自分のやりやすいほうを選択するとよいでしょう。
③日付をいれる
遺言者は遺言の作成日を必ず自書しなければなりません。これは遺言者が遺言作成時に遺言能力を有していたか否かを判断するためと、2通の異なる内容の遺言書があった場合の前後を決定するための重要な基準となるためです。
④署名・押印する
当然ですが署名・押印も必須事項です。署名だけではダメですよ。押印は拇印や認印でもよいと考えられていますが、判読が難しかったり信憑性という面から、できれば実印を押しておくべきでしょう。
以上の要件を満たせば法的に効力のある遺言書は完成です。簡単ですよね。ただ、一般的な遺言書でしたらこれで可能ですが、特殊なケースや、より相続人や受遺者に配慮した遺言書が必要な場合は専門家に相談するようにしましょう。
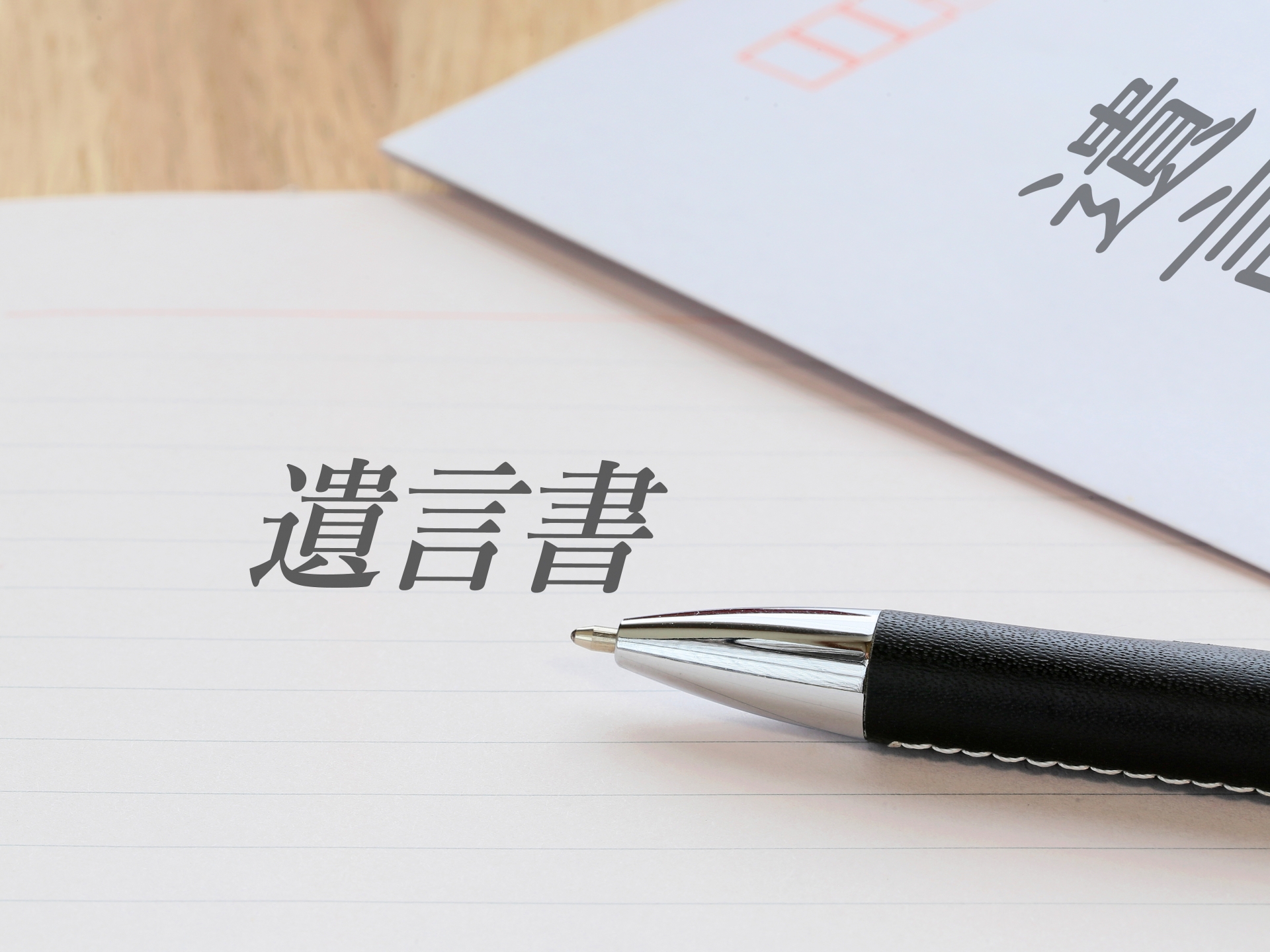


コメント